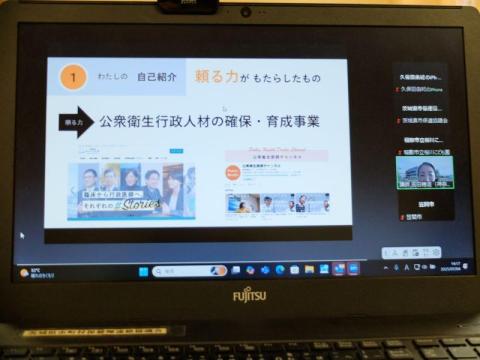 講師 吉田 穂波 氏
講師 吉田 穂波 氏
|
■研修名 茨城県市町村保健師連絡協議会 水戸・日立ブロック合同専門研究会
■開催日 令和7年7月4日(金)14:00~15:30
■開催形式 オンライン研修(Zoom)13:40より入室
■講師 神奈川県立保健福
祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科
教授・医師・医学博士・公衆衛生学修士
吉田 穂波
■参加者 茨城県市町村保健師連絡協議会会員等(保健師) 185名(31市町村)
■研修テーマ 行政保健師の成長をうながす受援力のススメ
■研修内容
行政保健師の世話にならない人はいない。すべての住民の生きるインフラが、自治体の保健福祉医療行政のシステムである。その中での保健師の仕事・立場の中で、保健師はいいことをしても感謝や労いを受けにくく、大きな感情労働の中で疲弊している。保健師自身は一生懸命やっているつもりでも、なかなか受け止めきれない困難に直面したり、多大なる心理的負担の中、前例が通用しない状況、どうしたらいいのかわからないことがある。
今回の研修で、頼るスキル・受援力について、保健師が現場・実践の場で使える構成になっている。なぜ私がこの頼るスキルに出会い、どう活用しているかについての自己紹介、なぜ保健師が頼るスキルを学ぶのか、どう使っていけばいいのか、そして行政保健師の強みを活かすための頼るスキルについて話す。
研修終了後に、使えるスキルとして自分を守り・支えるだけでなく、自分の励ますツールだと思えるようになればと思う。そして、自分自身が頼る力を身につけ発揮することで、自分にとって頼ってほしい・支えたい・役に立ちたい人がどのようにすれば頼りやすくなるのかに気づき実践につながっていければと思う。
[研修で大事にしたいポイント]
今回の研修では、チャットで考えを共有し、学びを深める。その中で、自分自身が主役であり、どう役立てるか、主体的に攻めの姿勢で参加できるようにすることを大事にしてほしい。一期一会、大勢の人と時間を共有することで新しい知識や刺激を受けてほしい。そして、自分とは別の世界や領域などの新しい考えを自由に受け入れる柔軟性をもって受けてほしい。
また、チャットで発言しやすいようにハウスルールを3つお願いしたい。誰にも後ろ指を刺されない・陰口を言われない・こそこそと後ろで揶揄されない・何を言っても否定されない・批判されないという「心理的安全性」が高い環境の方が高いパフォーマンス生み出し、いい成果を上げると言われている。今回の研修でも、全員フラットでこの場はみんな対等な立場であり、「いいね!」を口にする褒め合いマインド、拍手で場を盛り上げる大きな拍手をお願いしたい。
[わたしの自己紹介(なぜ自分がこの頼るスキルに出会ったのか)]
1998年に聖路加国際病院で研修医を始め、当初、私は一生、産婦人科医として働いていていくと考えていた。その後、医学博士号を取得し、夫の留学でドイツ・イギリスに渡り、ドイツで子どもを授かってイギリスで育てた。その中で、社会システムが違うだけで、育てる親の気持ちやサポートが違うことを痛感した。
そして、私は病気ではなく健康にフォーカスを当てた仕事がしたいと思い、ハーバードの公衆衛生大学院で公衆衛生学を学んだ。そのことで難しい病気を治すのではなく、健康な人がいかに健康であり続けるか、そのことに貢献した方が、より地域の健康に貢献できるのではないかと思い、地域の社会システム・法律・制度の全ての方たちと一緒に働きたいと思うようになった。その後、東日本大震災が起き、保健・医療・福祉・介護の重要性などを痛感し、そうした経験から2012年から行政の中で働き、保健医療の政策に携わる方の手伝いをするに至った。現在も神奈川県で教育・研究・臨床に携わりながらも、自分自身も受益者・弱者・子どもを育てる立場として、保健所や自治体のお世話になっている。
私自身、自分の子どもが増えれば増えるほど、自分ではできないことも増え、自身の様々な立場の中で、頼ることが増え、頼ることでいろいろな方とつながることになった。そのお陰で世界のいろいろ方とボーダーレスにつながり、新しい視点を知ることができ、柔軟な思考が身についた。自分が困り、頼ったことで、自分の殻を打ち破るような体験をして、助けられれば、助けられるほど、お恩返しをしたい、貢献したい、いろんな人と交流したいという気持ちが強くなった。
これまで東日本大震災を経験し、そこで得た学びを他の地域・世代の人に生かしたり、社会人の方が学び直せるような公衆衛生大学院を立ち上げたり、神奈川県ではプレコンセプションケアなど女性の健康支援策、自分がどうしてほしかったかということをもとに公衆衛生行政人材の確保や育成事業にも携わってきた。
自分一人だけではできなかったことをいろんな人に頼り、教えてもらうことでできるようになったと実感している。
[質問1:頼ることで助かったエピソードは?(チャットで参加者が発言)]
・母に頼ることで仕事に邁進できた
・夫に頼ってリフレッシュできた
・困難事例など課の中で声に出して共有することで周りの先輩たちなどのいろんな意見や経験などを聞き、助かった、視野が広がった
・ケースワークで病院や保育園、幼稚園に見守りを頼ることで話がうまく進んだ
・乳腺炎になった際に病院に頼ったことで助かった
・日常的に課内の保健師で相談することでいろいろな視点で考えることができている
・子育て中の転職活動、夜泣きの中の転職のための勉強、家族に協力してもらい前向きに転職活動に向き合えた
・保健師という職業であっても保育園に子育ててもらったというほど、お世話になった
・仕事につまずいたときに先輩や同僚の助言やサポートを得て困難を乗り越えられた
・東日本大震災で助けてもらった
・娘が学校に行けなくなったときに、同僚に話を聞いてもらって、気持ちが軽くなった
[頼ったときとき、頼られた方との関係は、どう変わったか]
頼った時、相手は迷惑そうな態度だったか。実は、むしろ、うれしくて、誇らしく、何でもするよという表情や姿勢ではなかった。頼ることは、相手にとっては、誇りとなり、喜びとなり、頼られているという自信を与える。
頼ることは、弱いから、情けないから、できないから、といった後ろめたさや蟇目もあるかもしれない。しかし、勇気を出して頼ることは乗り越えようという強さの表れである。そして、相手にとっても人の役に立ちたいという気持ちを引き出し、お互いの関係性を良好にする。
[行政保健師の頼る力 なぜ今日学ぶのか]
私自身、もともとは頼れる人間ではなかった。しかし、二進も三進もいかなくなり、頼ったときに、意外に頼ることは大事なことだと実感した。そこで、頼ることのメリット・デメリットについて調査や文献などで調べると、頼ること、頼られること、人の役に立つことが、いかに個人や地域の健康指標の向上に役に立っているかという調査結果が見つかった。
研究結果では、頼ることで、相手の自己効力感・自己肯定感・自信を引き出すことができることが明らかになってきている。人に頼られる・人に必要とされることが、ソーシャルキャピタル(生きがい指標)を上げ、健康寿命を延ばし、地域の自殺率を減らすという研究結果もでている。
頼るということは、責任感の強さや育てられ方などの影響で否定的に捉えることがあるが、頼ることは相手への信頼や尊敬の証となり、会話のきっかけ、知り合うきっかけになり、地域でつながり合い、地域の孤立・孤独予防になる。頼ることで、つながり、自分や相手の強みが広がる。
[受援力とは]
「受援力」とは元は内閣府が防災用語として、災害が起きたときに他の地域から支援を受ける体制を用意しておこうという考えから作られた。
支援をする・されることは、時として上下関係を生むことがある。支援をする方が上で,支援される方が下になり、支援を受けづらいことにつながる。災害時、私自身も頼ることができず、限界になり、バーンアウトしてしまい、自分の仕事を手放さざるを得なくなり、返って無責任になってしまった。
責任感や使命感が強い人は頼れないため、頼りやすくなる解決策はないかと考えた。困っていたら頼ればいいといっても、蟇目を感じやすく、頼れない。考え方や捉え方を変えるのではなく、行為・行動・スキルとしてSOSを出せないかというところから「受援力」に繋がった。
抱えこむ人、遠慮する人、心優しい人、自身のない人、こういった人たちは社会全体ではとても貴重な人であり、頼ることをポジティブに考える必要がある。
自分ですべてを引き受ける人は、「助けてと言えず孤立」→「自己肯定感下がる」→「自業自得・迷惑をかけるという呪縛」→「SOSを出すハードルを上げる」→「助けてと言えず孤立」・・・という悪循環につながる。自己肯定感も低い人は、受援力も低くなりやすい。
日本は若者の自殺が高く、15-39歳の死因の1位は自殺であり、他の国では見られない傾向である。困ったときに、他の人に助けを求めることができれば、こういった状況にならないのではないか。では、どうすれば頼るスイッチを入れられるのか。
頼ることは、能力の一つである。頼って当たり前の雰囲気を作ることで、頼った相手も頼りやすくなるということが大事である。
[受援力を発揮するには]
頼ることのハードルを下げるキーワードとして、受援力を発揮するには K「敬意」、S「存在承認」、K「感謝」が必要である。
K「敬意」: 相手は自分が頼るに値する存在である理由を伝えることが大事
「あなただから、頼みたい」「〇〇さん、今いいですか」
S「存在承認」:相手がいて、受け止めてくれたということが大事
「聞いてくれて、嬉しい」「助かる~」
K「感謝」:謝る言葉ではなく、感謝の気持ちが大事。罪悪感も軽くなる。
「話しただけで楽になった」「話せただけで感謝」
一言でも、相手への感謝・敬意を表現する。自分をみじめに貶めるのではなく、相手へ感謝する。ごめんではなく、あなたにお願いしたい!ということで、頼るハードルを下げる。
[受援力のその先へ]
頼った時に、もし断られたとしても、誠実に対応する。頼ったからと言って、全てOKになるというわけではない。断られることもある。
頼るときの心構え
1. 人の力を引き出す言葉を使う
断られた時の返し方(前向き質問)を準備しておく。
いつだったらいいですか?どんなものだったらいいですか?誰に聞いたらいいですか?
2. 感謝する
断られても「ありがとうございます」
3. フィードバックだと受け止める
軌道修正や改善するために活用する。自分への批判や個人攻撃とは受け取らない。
感情・機嫌ではなく事実を捉える。
4. 自分の心を満たす
会話や音楽、読書、入浴など自分に優しくして、自分のこころを満たす。右脳を活用!
保健師は誰かに与えることに慣れているが、誰かから与えられることになれていない。しかし、頼ることは自分だけでなく相手にとっても人の役に立ちたいという本能を満たすことにつながる。そのことで、自分の孤立も相手の孤立も守れる。
[受援力を広めるためにはどうすればいいか]
頼ることがいいことということが大前提である。
・困っ「たら」頼っていいんだよ
・頼っ「ても」いいんだよ
という表現はよくない。
「頼った方がいい」という考え方がよい!頼ることで、お互いの強みを出していくことにつながり、助け、頼り合える。
[質問2:受援力(頼る力)を発揮したらうまく進みそうなことは何ですか?(チャットで参加者が発言)]
・困難ケースの支援際、いろいろな部署に相談したら、解決の糸口がつかめそう。
・その人それぞれの強みを生かせる。
・療養休暇に入る人が減り、最終的に業務負担が軽減される
・家庭内の家事を分担すれば、早く眠れる
・それぞれの得意なことがオープンにできれば、お互いに助け合える
・業務改善する際に、いろいろな方から意見をもらうことができたらうまく進む。
・困難ケースの時に他の関係機関とつながりができる。相手との垣根が下がる。
・それぞれ得意なことを生かせば、無理なく楽しく仕事ができる環境が作れる。
・仕事を見える化することで、お互いがわかり頼りやすくなる。
・頼りやすくすること、相手の特性も活きる。強みを伸ばせる。
・経験者に求めることで企画内容の幅が広がる
[行政保健師の強みと活かし方 頼る力を活かそう!]
グループワーク1(チャットで参加者が発言)
中堅期保健師で、保健師が複数いる保健衛生部門から他部門へ異動後、住民への対応に戸惑い、先輩や周囲に頼れず、孤立感が強まっている。
問い:保健師が頼りやすい雰囲気を作れるようなアドバイスはあるか?
・挨拶や普段の雑談などのコミュニケーション「困ってることなーい?」
最近オンラインが多くなり、挨拶や雑談がなくなってきた。心理的安全性を高めるのが、挨拶や雑談だったりする。
・こちらから声をかけて、首を突っ込んでいく。
・定期的に保健師で集まり、困っていることを話す。
[受援力文化と働く人の健康]
〈受援力を発揮〉
管理職:新任の不安を理解し、フォローアップする
中堅:経験を共有し、相談しやすい雰囲気を作る
新任:先輩に積極的に声をかけ、上手に助けを借りる
↓
〈ポジティブな影響〉
管理職:困っている後輩に寄り添うことで自分自身の孤立を防ぐ
中堅:自分の経験を活かし気軽に声をかけることで気づきにつながる
新任:初心を忘れずわからないことは積極的に質問・相談することで成長
グループワーク2(チャットで参加者が発言)
新入保健師の立場から:事務作業が多く保健師の仕事としてモチベーションが下がる。仕事というよりは職場内の人間関係に生きづらさを抱える。自分では努力しているが、完璧主義・融通が利かない・こだわりが強いなど特性があり、だんだん疲れてきた。
問い:若手が不安な気持ちを認め周囲に頼ることを躊躇しないような雰囲気づくりのためにはどうしたらいい?
・忙しい中でも否定せず聞き入れる。
・成功体験を積み重ねられるように簡単な課題や役割を与える。
・一人で難しければ、先輩たちと一緒に行動できるようにする。
・成功体験を積めば、仕事にも前向きになれる。
グループワーク2(時間の関係上チャットでの発言は省略)
周りの同僚の立場から:上記のような方に振り回されないような一貫した気持ちの持ち方、本人への声のかけ方、アドバイスの仕方に悩んでいる。
問い:振り回される周りの職員はどのような気持ちの持ち方や心構えを準備しておくと良いと思うか?
頼られても断らなければならないときは上手な断り方としてDESC法がある。
DESC法:アサーティブネス
D(Describe):できない理由を説明
E(Express):気持ちを表現する
S(Specify):具体的な提案をする
C(Choice):選択枝や代案を示す
グループワーク3(時間の関係上チャットでの発言は省略)
問い:縦割りの壁を超えるためのアイデアはあるか?
行政保健師の強みは、専門知識、支援経験、連携能力、倫理観、責任感、事業企画立案である。その中で、保健師の強みはどこの部署でも組織横断的に、サイロメンタリティを超えて保健師は繋がれる。
人間関係を駆使しながら、他の保健師と課を超えてつながれる。同じ保健師として最強の共感できるポイントになる。
組織横断力である「メタ・リーダーシップ」、信頼関係やネットワークである「コネクター」を駆使することが、頼る力・つながる力を活かすことにつながる。
[質疑応答]
時間の関係上、アンケート等により質疑は個別に受け付けることになる。
|
|
